独奏協奏曲はヴィヴァルディが発明した。
リズム・メロディー・ハーモニーは音楽をなりたたせている「音楽の三要素」といいます。ジャズはプレーヤー間で厳密なルールを決めて、守っています。大事なのがテンポ。奏者全員がテンポを守って、完璧なグルーヴを目指します。クラシック音楽でテンポは伸び縮みします。ジャズでそのようなことをしたら演奏はとたんに崩壊してしまいます。
そのクラシック音楽とは〝Classic〟と言う通り、古い音楽のこと。昔の音楽、とうの昔に天に昇った作曲家たちの音楽のことで、ピアノ音楽も、協奏曲も、交響曲も、オペラも歌曲もリートも、ひとまとめにしてしまったもの。ジャズ全盛期に生まれたレコード・ビジネスが便宜上設けた。内容は多様性極まりなく、バッハは教会のために宗教曲を毎日書いた。モーツァルトは貴族が喜ぶ音楽を書いていたので、ベートーヴェンの運命のような曲を書く必要はなかった。食事の伴奏にジャ、ジャ、ジャ、ジャーンはないでしょう。
そのクラシック音楽とは〝Classic〟と言う通り、古い音楽のこと。昔の音楽、とうの昔に天に昇った作曲家たちの音楽のことで、ピアノ音楽も、協奏曲も、交響曲も、オペラも歌曲もリートも、ひとまとめにしてしまったもの。ジャズ全盛期に生まれたレコード・ビジネスが便宜上設けた。内容は多様性極まりなく、バッハは教会のために宗教曲を毎日書いた。モーツァルトは貴族が喜ぶ音楽を書いていたので、ベートーヴェンの運命のような曲を書く必要はなかった。食事の伴奏にジャ、ジャ、ジャ、ジャーンはないでしょう。
1876年にセルビアとモンテネグロはヘルツェゴヴィナ蜂起を支援するためオスマン帝国に対し宣戦を布告します。しかし、オスマン軍は速やかにこの両国を打ち破り、さらにはブルガリアにおける反オスマン反乱も鎮圧してしまいます。
それを待ってたとばかりに、ロシアはオーストリア=ハンガリー帝国と秘密協定を結んで中立的立場をとることを約束させると、こうなると、その戦いをロシアが引き継ぐかたちで、1877年にこの戦争に介入することになります。数世紀にわたる「露土戦争」のはじまりです。長引く戦争、ロシアはスラブ民族独立のための戦争であるという大義名分を掲げて、汎スラヴ主義的心情に訴えるという手法をとりました。そのため、ロシア国内でも戦争協力の動きが巻き起こり、ニコライ・ルビンシュテインが負傷兵のための基金募集のために演奏会を企画したり、その呼びかけにチャイコフスキーもすみやかに応えます。
それを待ってたとばかりに、ロシアはオーストリア=ハンガリー帝国と秘密協定を結んで中立的立場をとることを約束させると、こうなると、その戦いをロシアが引き継ぐかたちで、1877年にこの戦争に介入することになります。数世紀にわたる「露土戦争」のはじまりです。長引く戦争、ロシアはスラブ民族独立のための戦争であるという大義名分を掲げて、汎スラヴ主義的心情に訴えるという手法をとりました。そのため、ロシア国内でも戦争協力の動きが巻き起こり、ニコライ・ルビンシュテインが負傷兵のための基金募集のために演奏会を企画したり、その呼びかけにチャイコフスキーもすみやかに応えます。
チャイコフスキーの音楽には聴く人を一瞬でぐっと引き込む魅力があります。思わず口ずさみたくなるようなメロディにあふれていて、親しみやすい、でもなんど聴いても飽きない味わい深さがある。それがチャイコフスキーの魅力でしょう。終生に渡ってモーツァルトのことを敬愛していたチャイコフスキーは、モーツァルト的なスタイルを借りてきて、その中にチャイコフスキー流の抒情的な楽想を注ぎ込んでいきます。
チャイコフスキーの音楽にスラブのホコリ臭さは似合わない。言い換えれば、スラブのホコリ臭さを感じたくてチャイコフスキーを聴かない。チャイコフスキーとブラームスのヴァイオリン協奏曲は同じ1878年に書かれています。が、モーツァルトに対する絶対的な尊敬とは対照的。チャイコフスキーはブラームスの作品を評価せず、「並の人間が天才として認められている」と手厳しい言葉を残しています。
チャイコフスキーの音楽にスラブのホコリ臭さは似合わない。言い換えれば、スラブのホコリ臭さを感じたくてチャイコフスキーを聴かない。チャイコフスキーとブラームスのヴァイオリン協奏曲は同じ1878年に書かれています。が、モーツァルトに対する絶対的な尊敬とは対照的。チャイコフスキーはブラームスの作品を評価せず、「並の人間が天才として認められている」と手厳しい言葉を残しています。
日本ではピアノ教育を確立させた井口基成と安川加壽子が、ともに「ノイエ・ザッハリヒカイト(新即物主義)」派の門下生(それぞれイーヴ・ナット門下とラザール・レヴィ門下)であったため、新即物主義が主流になっている。ピアノ・コンクールのほとんどが「ザッハリヒカイト」時代(戦後)にスタートしていることと、日本のピアノ教育が「門下制」であるため、なかなかその「伝統」が断ち切れないために、「楽譜に忠実に」「テンポをきちんと守って」という弾き方を指導される。
故にドビュッシーの音楽は好まれているし、ドビュッシーのピアノ曲の邦人演奏は優れている。
積み重ねてきたものというのは音楽にはいらないし、新たな答えを見出そうというものでもない。まさに一糸乱れぬアンサンブルと強靱なオーケストラの響きは、指揮者の棒先三寸。オーケストラの楽員に奪い合いはいらないし、指揮者の棒先に同調すれば、指揮者が決めた音楽になる。記録という言葉さえ虚しいもの、未来を待つこともない。
ところが日本人ピアニストが「ザッハリヒカイト」的なコンクールで優勝できないのは、そんな「ザッハリヒカイト」派で育ったところにあるのではないだろうか。と考えもします。「白か黒か」の間には、灰色のグラデーションもあれば、白と黒の市松模様も斬新だ。作品や作曲家によって変わるはずのものでもある。『これは石畳に当たる雨音です、ここはにわか雨です。』『これは虹の音楽です。』ドビュッシーは「ザッハリヒカイト」に音楽を書いたし、それを良しとしたが、ドビュッシーは基本「ロマンティシズム」の作曲家なのだ。日本から外へ飛び出した内田光子は別格だが、アルフレッド・コルトーは日本からは出てこない。
故にドビュッシーの音楽は好まれているし、ドビュッシーのピアノ曲の邦人演奏は優れている。
積み重ねてきたものというのは音楽にはいらないし、新たな答えを見出そうというものでもない。まさに一糸乱れぬアンサンブルと強靱なオーケストラの響きは、指揮者の棒先三寸。オーケストラの楽員に奪い合いはいらないし、指揮者の棒先に同調すれば、指揮者が決めた音楽になる。記録という言葉さえ虚しいもの、未来を待つこともない。
ところが日本人ピアニストが「ザッハリヒカイト」的なコンクールで優勝できないのは、そんな「ザッハリヒカイト」派で育ったところにあるのではないだろうか。と考えもします。「白か黒か」の間には、灰色のグラデーションもあれば、白と黒の市松模様も斬新だ。作品や作曲家によって変わるはずのものでもある。『これは石畳に当たる雨音です、ここはにわか雨です。』『これは虹の音楽です。』ドビュッシーは「ザッハリヒカイト」に音楽を書いたし、それを良しとしたが、ドビュッシーは基本「ロマンティシズム」の作曲家なのだ。日本から外へ飛び出した内田光子は別格だが、アルフレッド・コルトーは日本からは出てこない。
1972年の恩師ディアギレフの生誕100年を記念して録音したロシア・バレエ団のために書かれたバレエ音楽集
通販レコードのご案内FR GUILDE SMS5227/28 マルケヴィチ モンテカルロのセルゲイ・ディアギレフ
鋭い眼光と長い指揮棒を駆使し、楽員を一糸乱れず統率し、楽曲を切れ味鋭く、聴かせどころの盛り上げをダイナミックに表現した凄さでマニアに大人気の20世紀を代表する名指揮者、イーゴリ・マルケヴィチ(1912.7.27~1983.3.7)。ピアノをコルトーに、和声と作曲をナディア・ブーランジェに学びました。
ロシア・バレエ団の主宰者ディアギレフに依頼されたピアノ協奏曲(1929年作)で、作曲家としてデビュー。1930年、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団で自作を振って指揮者デビュー。その後ヘルマン・シェルヘンに指揮法を師事し、本格的に指揮活動に入りました。日本へも度々来演し、1960年の旧日本フィルへ客演した際のストラヴィンスキーの〝春の祭典〟の名演は語り草となっています。本盤は、1972年の恩師ディアギレフの生誕100年を記念して録音したロシア・バレエ団のために書かれたバレエ音楽集。
セルゲイ・ディアギレフはロシアの芸術プロデューサーで、ニジンスキーを擁した伝説のバレエ団「バレエ・リュス」の創設者として歴史に名を残しています。ストラヴィンスキー「火の鳥」や「春の祭典」、ラヴェル「ダフニスとクロエ」など数多くの委嘱作品を世に送り出し、バレエを総合芸術に高めた偉人です。
ロシア・バレエ団の主宰者ディアギレフに依頼されたピアノ協奏曲(1929年作)で、作曲家としてデビュー。1930年、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団で自作を振って指揮者デビュー。その後ヘルマン・シェルヘンに指揮法を師事し、本格的に指揮活動に入りました。日本へも度々来演し、1960年の旧日本フィルへ客演した際のストラヴィンスキーの〝春の祭典〟の名演は語り草となっています。本盤は、1972年の恩師ディアギレフの生誕100年を記念して録音したロシア・バレエ団のために書かれたバレエ音楽集。
セルゲイ・ディアギレフはロシアの芸術プロデューサーで、ニジンスキーを擁した伝説のバレエ団「バレエ・リュス」の創設者として歴史に名を残しています。ストラヴィンスキー「火の鳥」や「春の祭典」、ラヴェル「ダフニスとクロエ」など数多くの委嘱作品を世に送り出し、バレエを総合芸術に高めた偉人です。
- そのディアギレフの晩年に若きマルケヴィッチは薫陶を受けており、バレエ・リュスとゆかりの深いモンテカルロ管を率いて収録した本作に対する思い入れは特別なものがあったでしょう。ロシア音楽を得意とするマルケヴィッチがあえてフランスのバレエ作品だけをセレクトした通好みの2枚組です。
かつて世界最大のレコード通販会社として君臨したコンサートホール・ソサエティ(略称CHS)は、スイスを本拠地として、英米独仏だけでなく遠くアジアの日本などに販売網を広げていました。残念ながら経営に行き詰まり、70年代前半倒産しましたが、EMI、DECCA、COLUMBIAと云ったメジャーレーベルから漏れた隠れた演奏には名演も多く、貴重な文化遺産となっています。このGUILDE INTERNATIONALE DU DISQUEは、CHSのフランス版で、クオリティに差はありません。
スタインウェイ・ピアニストとしての面目躍如
通販レコードのご案内NL PHILIPS A02322L イングリッド・ヘブラー モーツァルト ピアノソナタ選集第11番/第9番/第8番
イングリッド・ヘブラーほど、その主要レパートリーをモーツァルトに特化して演奏をし続けているピアニストは稀であるといえよう。彼女自身モーツァルトと同じオーストリア出身と云うことも関係しているのかもしれません。
西欧の肖像画では衣装に細かく美しいレースの刺繍が施されている絵を多く見るが、ヘブラーの演奏はまさに細く輝く糸で精巧に編まれた刺繍細工を見ているような気持ちにさせてくれる。
まるでモーツァルトを際立たせるかのように、丹念に、丹念に彼の作品を美しく飾ることに専念している。音楽性と技巧をひたすらモーツァルトの音楽に奉仕させるという姿勢を貫いている。
西欧の肖像画では衣装に細かく美しいレースの刺繍が施されている絵を多く見るが、ヘブラーの演奏はまさに細く輝く糸で精巧に編まれた刺繍細工を見ているような気持ちにさせてくれる。
まるでモーツァルトを際立たせるかのように、丹念に、丹念に彼の作品を美しく飾ることに専念している。音楽性と技巧をひたすらモーツァルトの音楽に奉仕させるという姿勢を貫いている。
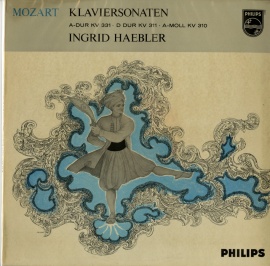
- イングリット・ヘブラーは本盤1960年代フィリップスに録音したモーツァルトのピアノ作品全集の素晴らしさで知られている。刺繍職人の素晴らしい細工が、いつまでも輝きを放ち、色褪せることのないように、何の不足もない。ヘブラーの玉を転がすようなタッチが美しいし、フィリップスの暖かい録音もいい。
録音はヘブラーが丹念に、さらに丹念に練習し、納得ゆくところで進められてゆく。録音セッションの合間の食事のときでも、ヘブラー心はここにあらず、さっさと自分の部屋に引き上げると、夜起き出して、ホールで自己鍛錬に集中するアーティストだ。彼女が練習の間はレコーディング・スタッフはただひたすら待つのみである。その潔さとあくまでも古典派の音楽へのアプローチとしての自由自在な表現が彼女の到達しえた解釈なのだろう。
驚くべき透明さや精緻とバランスを持っている美の結晶・セルが追い求めた理想のモーツァルト
通販レコードのご案内US COLUMBIA MS6858 セル/クリーブランド管 モーツァルト 交響曲第28番/第33番/フィガロの結婚序曲
セルの最大の業績はオハイオ州の地方都市クリーブランドのオーケストラを、大都会のニューヨーク、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス各オーケストラに比肩する、いや場合によっては凌駕する全米屈指の名門オーケストラに育て上げたことではないでしょう。その演奏スタイルは独裁者と揶揄されたセルの芸風を反映して、驚くべき透明さや精緻とバランスを持って演奏することであったという。
- セルはまたオーケストラのある特定のセクションが目立つことを嫌い、アンサンブル全体がスムーズかつ同質に統合されることを徹底したとも云う。こうしたセルの演奏からまず伝わってくるのは、あたりを払うような威厳であり、作品の本質を奥底まで見つめようとする鋭い視線が窺える。
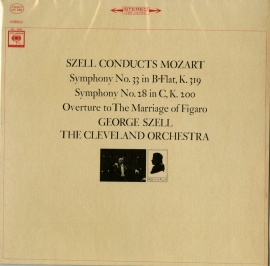
絶頂期のクリーヴランド管弦楽団の音色の美しさも特筆すべきもので、オーケストラ全体がまるでひとつの楽器のように聴こえます。音がギッシリ詰まって密度が高い証左か、とにかく、セルの棒にかかると、実に格調高く、またスケールの大きなものとなる。さらに、旋律の歌わせ方などは、セルがハンガリー出身であることも思い出させてくれます。ここに西側の指揮者は真似できない何かが有ります。
カラヤンがクリーブランドで、セルがベルリンで指揮をしていたとしたら、今聞くクラシック音楽のイメージは変わっていたか。セルと同時期に活躍した指揮者といえばマリナー、クレンペラー、ベーム、カラヤンは交響曲全集を残したモーツァルト振りだった。彼らの演奏したモーツァルト演奏は今日において重要な名盤、名演のガイドラインであることに間違いない。
今日においてベートーヴェンも大オーケストラで演奏するよりも小オーケストラで演奏する機会が非常に多いわけだが、先駆けとして彼らの演奏があって、スタンダードになったと言っても良いだろう。
カラヤンがクリーブランドで、セルがベルリンで指揮をしていたとしたら、今聞くクラシック音楽のイメージは変わっていたか。セルと同時期に活躍した指揮者といえばマリナー、クレンペラー、ベーム、カラヤンは交響曲全集を残したモーツァルト振りだった。彼らの演奏したモーツァルト演奏は今日において重要な名盤、名演のガイドラインであることに間違いない。
今日においてベートーヴェンも大オーケストラで演奏するよりも小オーケストラで演奏する機会が非常に多いわけだが、先駆けとして彼らの演奏があって、スタンダードになったと言っても良いだろう。
ジョージ・セルはオーストリア=ハンガリー帝国時代のブタペストで生まれました。3歳からウィーン音楽院でピアノ、指揮、作曲を学び、11歳でモーツァルトのピアノ協奏曲を弾いてピアニストとしてデビュー。ヨーロッパ各地へ演奏旅行を行い、自作曲も披露、「モーツァルトの再来」とも評されます。作曲家・指揮者だったリヒャルト・シュトラウスに認められ、ベルリン国立歌劇場のアシスタント指揮者となったのは、18歳のとき。オーストラリアへの演奏旅行の帰途に第二次世界大戦が勃発、トスカニーニの援助でNBC響の客演指揮者として迎えられる形でアメリカにとどまり、帰国をあきらめざるを得なかった。
戦後早々にクリーヴランド管弦楽団の音楽監督に就任。経営陣から一切のマネジメントの権限を手に入れたセルは大改革を行います。楽団員の半分以上を解雇し、罵声を浴びせながらも徹底した訓練を行い、10年足らずで世界第一級のオーケストラに育て上げました。
そんな怖いセルがウィーン・フィルの客演に招かれたときのエピソードは有名です。ウィーン・フィルの団員たちが、彼の指揮に対して勇気を出して文句をつけたときのこと、セルはきっぱりとこう言ったそうです。
ギルドシステムの強かったアメリカの楽団スタイルを、固定メンバーとし、オーディションを勝ち抜いた精鋭たちによって構成したことでカラヤンのベルリン・フィルでもできなかった、セルが追い求めた理想のモーツァルト像を実現した。
経営難にあったクリーヴランド管に、リヒャルト・シュトラウス時代の大編成は望むことはできなかったろうが、小編成であるが故緩やかな楽章での色彩豊かなアンサンブル、疾走感あふれる演奏で響きが引き締まり、強靭さが増すことをリヒャルト・シュトラウスから学んだことでもあったのではないか。
戦後早々にクリーヴランド管弦楽団の音楽監督に就任。経営陣から一切のマネジメントの権限を手に入れたセルは大改革を行います。楽団員の半分以上を解雇し、罵声を浴びせながらも徹底した訓練を行い、10年足らずで世界第一級のオーケストラに育て上げました。
そんな怖いセルがウィーン・フィルの客演に招かれたときのエピソードは有名です。ウィーン・フィルの団員たちが、彼の指揮に対して勇気を出して文句をつけたときのこと、セルはきっぱりとこう言ったそうです。
わたしは諸君に招かれてきた。だから諸君は私を追い出すこともできる。つまり二つの道がある。諸君の馴染んだやり方でやるか、わたしのやりたいようにやるか。わたしは最初のやり方に賛成しない。だから第二の道しかないわけだ!感情移入を行わない禁欲的で厳密な解釈と終身雇用が日常だった日本では特に「冷徹な」指揮者とする評価が、米COLUMBIAの日本での発売元が、CBSソニーになったことも相まって、マイナスのイメージもあったが、楽譜に書かれている指示に正直であれば、作曲家のイメージした音楽が顕現するのです。
ギルドシステムの強かったアメリカの楽団スタイルを、固定メンバーとし、オーディションを勝ち抜いた精鋭たちによって構成したことでカラヤンのベルリン・フィルでもできなかった、セルが追い求めた理想のモーツァルト像を実現した。
経営難にあったクリーヴランド管に、リヒャルト・シュトラウス時代の大編成は望むことはできなかったろうが、小編成であるが故緩やかな楽章での色彩豊かなアンサンブル、疾走感あふれる演奏で響きが引き締まり、強靭さが増すことをリヒャルト・シュトラウスから学んだことでもあったのではないか。
http://img01.otemo-yan.net/usr/a/m/a/amadeusclassics/34-26063.jpg
October 29, 2021 at 11:45PM from アナログサウンド! ― 初期LPで震災復興を応援する鑑賞会実行中 http://amadeusclassics.otemo-yan.net/e1145313.html
via Amadeusclassics
コメント
コメントを投稿